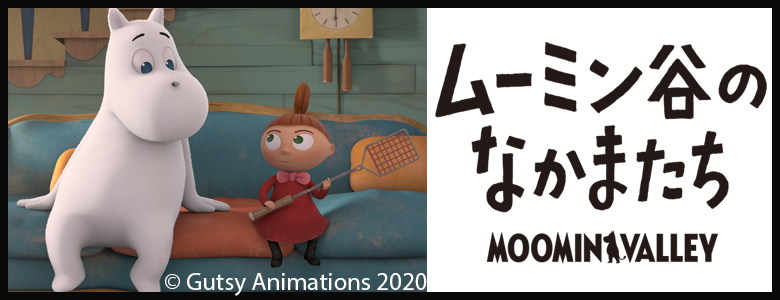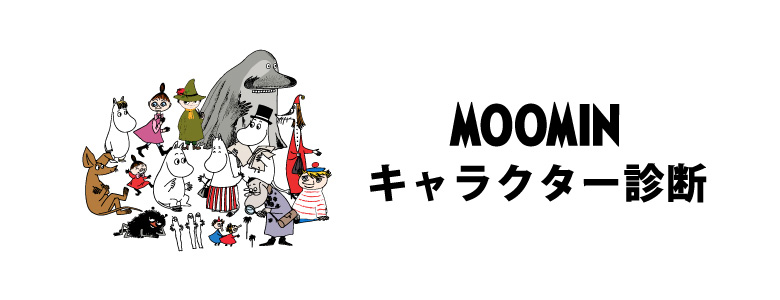(183)静寂と気配と島の秋【フィンランドムーミン便り】

3000人が暮らしていた群島は、夏の住人が去ると250人に。あちこちの家に、もう人の気配はない。
トーベ・ヤンソンが夏を過ごした群島ペッリンゲ。人生のどの段階にあっても、夏にはペッリンゲに戻ってきた。彼女が有名になってヘルシンキでの人間関係には歪が生じることもあり、画家仲間の嫉妬に至っては「そんないいがかり…」と思うようなこともあった。お前はムーミンで成功したんだから画家を助けるべきだとかいって絵画を持ち去った画家たちのこととか、聞いただけでもぞっとする。島の人たちは、トーベ・ヤンソンがムーミンでどんどん有名になっていくのを知りつつも、特別なことはしなかったという。
島の人々は基本的にそっとしておいてくれる。それは首都ヘルシンキのような無関心とはちょっと違っていて、どこか安心感があった。島に一人で過ごしていると、一人でやらなくちゃならないことは街のそれよりも多い。それでも、助けが必要なときに声をかければ誰かしらが助けてくれる安心感といったらいいか。
ペッリンゲは夏が終わると、島々に暮らす人たちの数は250にまで減少する。誰にも会わない日が続き、コテージ暮らしの私はお湯ひとつも薪をくべて作らなければならない。雨の日が多い秋は、木の皮が少し湿っていて、火を起こすことすら経験の少ない私には大仕事になったりする。でも、そうやって湿り気を感じたり、湯沸かし窯の薪がパチパチ鳴る音を聞いたり、窓を叩く風が一日のうちに激しさの度合いをどんどん変える様子、外に一歩でた時の秋の匂い。夏に出会ったものとは違うものの気配がそこここにあった。
秋の晴れた日に小さな女の子がひとり、畑の中を走っていた。気付かれないように近づいてみると、彼女は自分で作ったホビーホース(棒に毛糸の靴下などを用いた馬の頭をつけたもので、これで乗馬の競技を真似たりする)にまたがって走っていた。ギャロップしたり、障害を跳び越えたり、そしてふとした拍子に少女は転んだ。あとで聞けば、落馬したのだという。たった一人でいても、自然と関わり続け、自分の想像力で世界は広がっていく。この島で育った人たちからは、こういう話をよく聞いた。
人はおらず静寂に包まれた島にたった一人。紅葉した葉は落ち、畑のものが刈られても、そのがらんとした景色の中にはたくさんの気配が潜んでいた。それは決して怖いものではなく、一人で過ごす私に想像する楽しさや新しい発見を与えてくれるように思う。島を離れる前に、もういちど海を眺めに行こう。漁師が仕掛けた網の近くにいってみると、魚を物色しに来ていたのかアザラシがいた。頭を出してずっとこちらを眺めている。もし漁師の網にかかっていた魚を食い荒らしてしまったらと思えども、漁師に連絡する以外、どうするのが一番いいのかぱっと閃かない。島で自分のできることが少し増えたと思っていた矢先に、こうやって自分の無力さを突きつけられる。帰りの道中に、ムーミントロールの言動をあれこれ思い出した。いつまでたってもムーミントロールっぽいままの自分に、少しうんざりしながら。

葉が落ちて森の見通しがよくなると、夏には気づかなかったような獣道を見つけたりも。
森下圭子