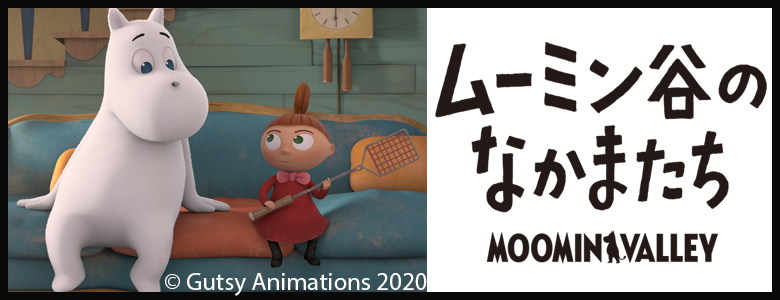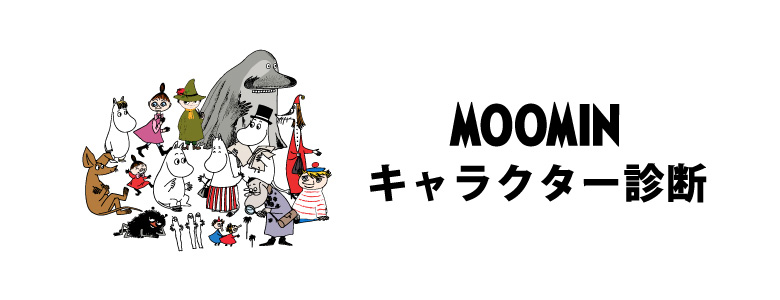(168)ムーミン谷の彗星とひと夏の冒険

1945年の夏。トーベ・ヤンソンはスナフキンのモデルとも言われる恋人アトス・ヴィルタネンと共に、彼が生まれ育ったオーランド本島の小さな村、サルトヴィークにいた。とはいえ、自分の誕生日も一人で過ごしたトーベ。夏の多くの時間を、ひとりで過ごしていたようだった。
自転車でイェータへ行く毎日。評伝によると、ノートを片手に『ムーミン谷の彗星』を執筆していたという。イェータとは、オーランド本島の北にある岩が特徴的な地域で、山もあり、少し歩けば足場ががらりと変わるほどに、岩肌や岩の様子が違った。
そういえば『ムーミン谷の彗星』にでてくる自然は、緑の多いムーミン谷とは様子が違う。海が干上がった景色は特に印象的だ。これまでとは勝手の違う足元を歩いている感じ、高低差の大きな風景。トーベがいつも夏を過ごしたペッリンゲに比べると、イェータの風景は緑が少なめで、そして規模が大きかった。いつものムーミン谷がペッリンゲなら、確かに『ムーミン谷の彗星』はイェータを彷彿とさせる描写が多い。
ムーミンという、個性的な姿の生き物をつくったトーベだけれど、実は物語を作るにあたっては、自然の細かい観察記録がノートに残されている。この花は何月何日に開花したか、どんな鳥を何月何日に見かけたか、それはペッリンゲにいるときも、さらにはムーミンのシリーズが終了してからも続いていた。
さらにムーミンを書くにあたって、トーベに欠かせないのが「読んでくれる人」の存在だ。ムーミンシリーズの最終巻『ムーミン谷の十一月』でも、夜ごとに、その日書いたものをトーベは朗読してくれたと、部屋を貸していた方が語っている。自分の創作をすぐに身近な人に見てもらうやり方は、実は両親が家族に対してやっていたことだった。
「孤独を愛する」側面に焦点があたりがちなスナフキンだけれど、物語を読んでいると、すばらしい聞き手でもあることに気づく。人の言葉を途中で遮ったりせず、まずはその人の声に耳を傾ける(ときに煩わしいと思うことがあったとしても)。
自分にとっては馴染みのない景色を歩き、そこで何かを書き記し、家に戻っては誰かに聞いてもらう。それはかつて『ムーミン谷の十一月』の制作の裏話として聞いたことであったけれど、そんな制作の方法が成立したのは、ムーミン小説の二作目、『ムーミン谷の彗星』からなのかもしれない。そんなことを考えたのも、オーランド諸島を旅しながら、何人かの人たちと「ムーミンのシリーズは二作目で大きく飛躍するけれども(一作目を本人は気に入っておらず、80年代はそれが絶版だということにほっとしている本人証言の音源が残っている)、そのきっかけは何だろうかと話し合った。
本人不在の今、確認することはできないけれど、馴染みのない景色どころか馴染みのないところを毎日歩き、自分の書いたものを聞いてくれ相談にのってくれるスナフキンのような人、アトスの存在。1945年のイェータをめぐるひと夏の冒険は、ムーミンの物語を創作するにあたっての、基盤を作ったのかなと想像している。ちなみにムーミン谷やキャラクターの設定についてはは、その次の作品『たのしいムーミン一家』で定まってきたと言われている。

森下圭子